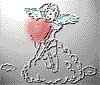 * 擬似恋愛 * <SP> 思いがけない竜司の告白に凪菜は大学で講義を受けていても、通学途中の電車の中にいても、嬉しさが込み上げてきて顔がニヤケてしまうのを抑えるのが大変だった。 だけど、あの温泉での撮影以来、竜司には逢っていない。 ───電話やメールでは話しているけど、やっぱり逢いたいな。 明るい空の下、手を繋いで歩いてみたい。 そんなデートが夢だった。 商社に勤める彼が忙しいことも十分わかっているし、こんなお子様な私に合わせるのは大変なんじゃないだろうか。 それにAV女優なんて…。 自分で決めたことだし、後悔はしていない。 この仕事をしていなければ、彼に出逢うこともなかったかもしれない、それでも…。 次の講義まで時間が空いているからと一人カフェテリアで休憩していた凪菜だったが、今まで携帯電話など仕事の連絡手段として使う程度のものだったのに今では彼と繋がっていられる唯一の物に。 そんなことを考えながら大事に手で握り締めていると電話が振るえ出した。 「もしもし、竜司さん?」 『凪菜。今、話しても大丈夫?』 「はい、次の講義待ちなので。竜司さんは、お仕事大丈夫なんですか?」 『全然平気』と明るい声で返してくる竜司。 忙しいはずなのに合間を縫ってはこうして電話を掛けて来てくれる彼、声を聞けただけでもわけもなく涙が込み上げてくる。 『あのさ。実を言うと今、大学の前に来てるんだよ』 「えっ、大学の前って…」 思わずガタンッと大きな音を立てて凪菜は椅子から立ち上がると、窓の近くへ走り寄った。 2階にあるカフェテリアからはわずかに正門が見えるのだが、チラチラこちらを覗き見ている竜司らしき男性の姿が確認できる。 ───ヤだっ。竜司さんったら、あんなところで…。 女子大に出入りする男性は限られていたから、このご時世不審者に間違われる可能性も高いというのに…。 「今すぐ、行きますから。そこで、待ってて下さい」 教科書とバッグを掴み、凪菜は急いで階段を駆け下りると正門に向かってひた走る。 逢いたいとは思ったけれど、まさかこんなところで逢うことになろうとは…思ってもみなかった。 「りゅ…じ…さ…っ…」 両膝に手をあてて、はぁはぁと息の荒い凪菜。 しかし、竜司の表情はどこか間の抜けたものに…。 それもそのはず、彼は普段の凪菜の姿を見たことがなかったのだから、目の前にいる彼女と記憶の中の凪菜を同一人物に重ね合わせるには少し時間が掛かるのかもしれない。 「凪菜?」 「りゅ…じ…さん、どうしたんですかっ…急に…こん…な…と…ころへ来て…はぁ…」 滅多に走ることのなかった凪菜には、この距離でさえもかなり息が上がってしまう。 途切れ途切れに話す彼女に、竜司もようやく彼女が一つになりかけてきた。 「たまたま、仕事で通りかかったのが凪菜の通う大学の前だったから。ちょっとでも顔が見られたらなんて」 「そうなんですか」 やっと落ち着いたのか、凪菜が竜司のことを見つめる。 初めて見るスーツ姿の彼に思わず目が釘付けになった。 素敵過ぎて…。 ───あっ。 道理で竜司の表情がいつもと違うと思ったら、この凪菜の姿を見たからだということに今更気付いた。 どうしよう…。 こんな姿、見られちゃって。 「ごめん。初め見た時、全然わからなかった」 「普段の私は、こうなんです」 「でも、どうして?」 「親もうるさいし、こうして目立たない格好をしている方が何かと都合がよかったので」 厳しい親と周りの派手めな子達との付き合いも面倒だった凪菜には、こうしている方が楽だったから。 でも、好きな人の前ではもう少し可愛い格好をしたかった。 あぁ…。 「そっか。俺もその方がいいと思うよ」 「え?」 「可愛い凪菜に悪い虫がつかないようにね」 可愛いなんて言われて、凪菜の頬が一瞬にしてピンク色に変わっていく。 彼女のあれやこれ、全部を知っているのは、恐らくここにいる竜司だけだろう。 …そう思ったら、ヤパイくらいに嬉しさが込み上げてくる。 「あのさ、少し抜けられない?」 「え?」 「せっかくだから、デートしよう」 「デート?」 「あぁ」と頷く竜司に凪菜は、少しの間考える。 入学して以来一度も講義をサボるなどということはなかったが、講義よりも何より今は竜司と一緒にいたい。 逢いたくて、そして憧れのデート。 「はい。私は大丈夫ですけど、竜司さんは?」 「俺?1時間くらいだったらね」 「じゃあ、決まり」と竜司は凪菜の手をさり気なく握り、傍から見れば女子大生を連れ去ってと思われるかもしれないから、不審に思われないように急いでその場を立ち去ることにする。 ───こんなことなら、もっと可愛い洋服を着て来るんだった。 髪型だって、それにこんなスッピンじゃなくてきちんと化粧もしてきたのに…。 それでも、握っている手から彼の熱と共に想いが伝わってくるような気がしてそれだけで幸せだと思えた。 大学の周りには女の子が好みそうなカフェやレストラン、可愛らしい雑貨屋さんなどがたくさんあって、講義が終わると学生でいっぱいになる。 まだ、この時間だとそんなにはいなかったから凪菜が竜司と歩いている姿を友達に見られることもない。 「凪菜はいつも、ここを通ってるのか?」 「はい。この通りを真っ直ぐ行くと駅なので、ここは毎日通ってますよ。帰りにお友達とお茶したり、ご飯食べたりもしますし」 こんな地味な凪菜には、そんなにたくさんの友達はいない。 それでも、仲のいい子達と帰りにお茶をしながらおしゃべりしたり、ちょっとお酒を飲みながらご飯を食べたり、普通の女子大生がしているようなこともしていた。 「だったらさ、案内してよ。凪菜がどういうところに行ってるのか、教えて欲しいな」 女子大に通っているのだし、お友達というのはもちろん女性だろうけど、凪菜がどんなところに行ったり話したりしているのか竜司は知っておきたかった。 「はい」と微笑む凪菜に案内されて立ち寄ったのは、ヘアアクセサリーのショップ。 髪型などいつも地味に纏めているだけの凪菜にはあまり縁のないような店ではあるが、撮影の時にこっそり身につけて行ったりもしているし、友達の間でもとっても人気がある。 「もしかしてこの前、髪を留めてたのってここで?」 「覚えててくれたんですね」 「もちろん」と領く竜司。 露天風呂で、髪をアップにしたあんなに色っぽかった凪菜を覚えていないはずがない。 …思い出しただけでも、下半身が熱くなってきそう。 「どれがいい?」 「え?」 「買ってあげる。えっと、凪菜にはこんな感じのがいいかな」 竜司が飾ってある中の一つを取って、凪菜の髪に合わせてみる。 キラキラとラインストーンが輝く、ゴージャスだけど渋めのカラーが今の季節にぴったりだ。 「似合うよ」 「でも…」 「いいって、これくらいお安いもんだよ。っていうか、安過ぎだけど。まぁ、一つくらい俺が買ってあげたものを持ってて欲しいななんてね」 「本当なら指輪とか、ネックレスとかの方がいいんだろうけどね」と話す竜司の本音だったかもしれない。 こんなふうに男の人に何かを買ってもらったりするのは初めてで凪菜は申し訳ないような、嬉しいような。 でも、「ほら、どれがいい?」と聞き返す彼に凪菜もお言葉に甘えておねだりすることにした。 「えっと、竜司さんに選んで欲しいです」 「俺?ん~センスないかもしれないよ?」 「そんなことないです。それ、すごく素敵ですよ」 「そう?だったら、俺はこれがいいなって思う。一番に目がいったんだ。凪菜にぴったりだって」と初めに手に取った物をもう一度凪菜の髪に合わせて鏡を見つめる。 後ろには彼の顔が一緒に映っているけど、今の自分と釣り合ってない…。 思わず、顔を背けてしまう自分がいた。 「決まり。これにしよう」 レジで可愛くラッツピングしてもらって、それを凪菜は大切に胸に抱えて二人は店を出た。 その後、また手を繋いでゆったりと道を歩く。 時計に日を向けると1時間のタイムリミットまで、もうそんなに時間がない。 ───このまま、時が止まってしまえばいい…。 そうは思っても、無理な話よね。 「あっ、ここ。とっても、チーズケーキが美味しいんです。私、すぐ太っちゃうから、あんまり来られないんですけど」 「ちょっと、寄って行く?」 「はいっ。でも、竜司さんは甘いものとか平気ですか?」 「そんなでもないけど、いいよ」 ───竜司さんって、甘いものはそんなに食べないのね。 少しずつだけど、こうやってお互いのことを知っていくのかな。 彼の後に付いてお店に入ると店内には甘い香りが漂っていて女性客で賑わっていたが、一斉に竜司に視線が集まる。 そんな彼に隠れるようにして凪菜は店員に案内された窓際の席に向かい合って座ると、凪菜はチーズケーキと紅茶のセット、竜司はコーヒーを注文した。 今の姿をあまり見られたくなかったし、きっと周りの人も釣り合わないって思ってる。 もっと彼の顔を見ていたかったけど、そんな思いがいつしか凪菜を俯かせてしまっていた。 「やっと逢えたんだから、もっとよく顔を見せて」 竜司の言葉は嬉しかったが、凪菜は顔を左右に振るだけで顔を上げることはできなかった。 そんな時、頼んでいた物が運ばれてきて凪菜の前に美味しそうなチーズケーキと紅茶が並ぶ。 「俺の顔は見たくない?」 「そんなっ」 反射的に顔を上げた凪菜は、彼の真剣な眼差しに目が離せない。 「ほら、そんな顔しない。笑って?凪菜の笑顔が見たいんだ」 「竜司さん…」 「これ食べたら、笑ってくれる?」と竜司が凪菜の前にあったチーズケーキを小さくフォークで取ると、彼女の口元に差し出す。 『何だか、子供みたい』 それにみんなが見てるのに…そう思ったけど、多分彼は食べるまでそのままにしていそうだったから、凪菜は黙ってそれを口に入れてもらう。 ───あ~美味しいっ。 ゲンキンだけど、美味しいものを食べるとどうして、いい顔になるのだろうか。 「そう、その笑顔。俺は、どんな凪菜も好きだから。あっ、でも俺の腕の中にいる時が一番かな」 「ベッドの中で」なんて言うものだから、凪菜は一気に頬を赤らめて両手で顔を覆ってしまう。 竜司にとっては、彼女のしぐさ一つ一つが愛おしいくてたまらない。 仕事の時の大胆さも、今みたいな冗談でもすぐに頬を染める彼女も全部。 「今度の休みの日には、ちゃんとデートしよう?迎えに行くから、その時は目一杯可愛くして。俺のために」 ───竜司さん…。 「はい。頑張って、可愛くします」 …その微笑が一番だよ、凪菜。 END ※ このお話はフィクションです。実在の人物・団体とは、一切関係ありません。作品内容への批判・苦情・意見等は、ご遠慮下さい。
誤字が多く、お見苦しい点お詫び申し上げます。お気付きの際はお手数ですが、左記ボタンよりご報告いただければ幸いです。 Copyright © 2005-2013 Jun Asahina, All rights reserved. |