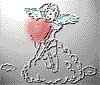 * 擬似恋愛 * <1> 「あの…今度の相手も、リュウジさんですか?」 「そうだけど、何か問題ある?」 「いえ…その」 相手がリュウジでは、何か不都合なことでもあるのだろうか? 稟花(リンカ)の人気は不動のものだったが、それに加えて男性からの支持も高いリュウジとのペアは特に評判がいい。 本来この業界ではあまりイケメンの男優は使わないのだが、男性にも憧れというものは存在するようで、リュウジを真似る若者は多い。 「どうかした?」 「他の方にしていただくことは、できませんか?決して、リュウジさんが嫌だとかそういうんじゃないんです」 市野には、なんとなくピンとくるものがあった。 もしかして…。 稟花はリュウジを好きになってしまったのではないだろうか? だから、こんな形でこれ以上関わりたくないと。 「稟花ちゃん、もしかしてリュウジさんのこと好きになった?」 「え…」 市野の鋭い読みに稟花はどう答えていいかわからない。 こういう仕事に就くことには少なからず不安もあったが、市野はいつだって本当の姉のように稟花に接していてくれた。 稟花にだって、リュウジとのペアが売れることは知っている。 それを自らの我侭で断っていいはずがないのだ。 「市野さん」 「稟花ちゃん、あたしで力になれるかどうかわからないけど、なんとかしてみる」 「我侭言って、すみません」 「ううん。逆のケースはよくあるんだけど、リュウジさんカッコいいものね」 男優の方が女優に惚れてしまうというケースはよくあるから、そういう面で相手を代えるということはあっても稟花のような場合は稀なのである。 リュウジはあの容姿で、性格もいいとくれば誰でも惚れてしまうだろうが、稟花のように演技でも体を合わせてしまえば尚更のことだろう。 「でも、リュウジさんには何と言うんですか?気を悪くされなければいいんですけど。それに市野さんは大丈夫ですか?」 稟花が相手を代えて欲しいなどと言えば、リュウジの方は自分が嫌なのではないかといらぬ詮索をするかもしれない。 それに市野の方にも少なからず、迷惑が掛かるのは避けられない。 「稟花ちゃんは、実はイケメンでない方が好みなのとでも言っておくわ」 これなら、リュウジも嫌な思いはしないだろうけれど…。 「とにかく稟花ちゃんは心配しないで、あたしに任せて。これで稟花ちゃんに辞められるよりはいいから」 「はい」 市野が胸にポンっと手を当てた姿を見て稟花は申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、できればリュウジとはもう関わりたくない。 それで辞めることになっても仕方ないと思っていた。 それから暫くして市野から相手を代えてもらったと聞いたが、リュウジの方は特に何も言わなかったらしい。 本当はリュウジがいいに決まっている、でも抱かれれば抱かれるほど想いが強くなる。 きっと、彼にも気付かれてしまうだろう。 そうなる前に手を打つしかなかった。 +++ 「リュウジさん、今回は申し訳ないんだけど稟花ちゃんの相手は別の人にしてもらってもいいかしら?別にリュウジさんに問題があるわけじゃないの。リュウジさんと稟花ちゃんのペアは人気があるんだけど、稟花ちゃんがたまにはもっとダサい相手の方がいいって」 市野は、リュウジの顔が一瞬曇ったのを見逃さなかった。 だから、先手を打つように理由を言ってしまったのだ。 「そうですか」 「残念?」 「え?」 リュウジは、市野の言葉にハっとした。 相手の変更は稟花の希望だという話だから仕方がないが、残念という思いは少なからずなかったとは言い切れない。 「リュウジさん、稟花ちゃんとだとすごく楽しそうだから、なんとなくそう思っただけ」 市野の言うように稟花以外の子では仕事という観点から、どうしても冷めた感じに取られがちだが、彼女の場合は違った。 初めは初心な稟花を安心させるために、マイクには拾われないような小さな声でアドバイスをした。 そんなリュウジのいう通りに彼女が反応を示してくれるのが、嬉しかったのだ。 だから稟花との時はとても楽しみだったし、それが表情に表れていたのかもしれない。 「そうかもしれません」 あまりにリュウジの素直な反応に意外だという様子の市野。 「稟花ちゃん。反応のひとつひとつが可愛いから、知らぬ間に引き込まれたみたいです」 リュウジが稟花を可愛いと思うのは、恐らく愛情からではないだろう。 もう、稟花はリュウジとペアを組むつもりはないはずだが、彼の方はそう思っていなかった。 +++ 「稟花ちゃんってさぁ、ダサい男が趣味なの?」 …え? 「あっ」 なぜリュウジがこんなことを言ったかというと、相手を代えてもらう口実に稟花はダサい男が好きだということにしておこうということになったからだった。 実際、稟花がそういう男性を好きではなかったが、この場はそう言っておかないとリュウジも納得してくれないだろう。 「えっ、はっはい。私、リュウジさんみたいなカッコいい男の人はダメなんです」 これでは、遠回しにリュウジを好きではないと言っているような気もしないでもないが…。 「それって、俺が相手じゃダメだってことなのかな?」 「そっ、そういうわけじゃっ」 そうじゃないと言おうと思うのだが、言えば言うほど墓穴を掘ってしまいそうだ。 「じゃあ、なんで?」 「それは…」 リュウジはわざと顔を近づけてくる。 ううう…。 そんなに顔を近づけられたら困るのに…。 「リュウジさんが相手だと、ドキドキするから」 「ドキドキ?」 周りのスタッフに見られているという恥ずかしさや緊張もあるが、それ以上に好きな相手に抱かれているのだということの方が大きくて、ものすごくドキドキするのだ だからといって、ここで好きだからとは口が裂けても言えないわけで…。 「いえ、あの…」 「稟花ちゃん、ちゃんと言ってくれないとわからないんだけど」 リュウジの目は真剣だ。 「ッコいいから───」 「え?」 初めの方がよく聞き取れなかったリュウジは、もう一度聞き返すが…。 いいところで、「稟花ちゃん、ちょっといいかしら」という市野の言葉に遮られてしまう。 「はい、今行きます。ごめんなさい、リュウジさん。私…」 「あっ、待って。稟花ちゃん」 彼女は一体、何と言ったのだろう…。 稟花の後姿をリュウジはただ、ジッと見つめるしかなかった。 ※ このお話はフィクションです。実在の人物・団体とは、一切関係ありません。作品内容への批判・苦情・意見等は、ご遠慮下さい。
誤字が多く、お見苦しい点お詫び申し上げます。お気付きの際はお手数ですが、左記ボタンよりご報告いただければ幸いです。 Copyright © 2005-2013 Jun Asahina, All rights reserved. |